地域の話題など、日々雑感―さんぽみちー
公共交通に関する講演会を開催しました。

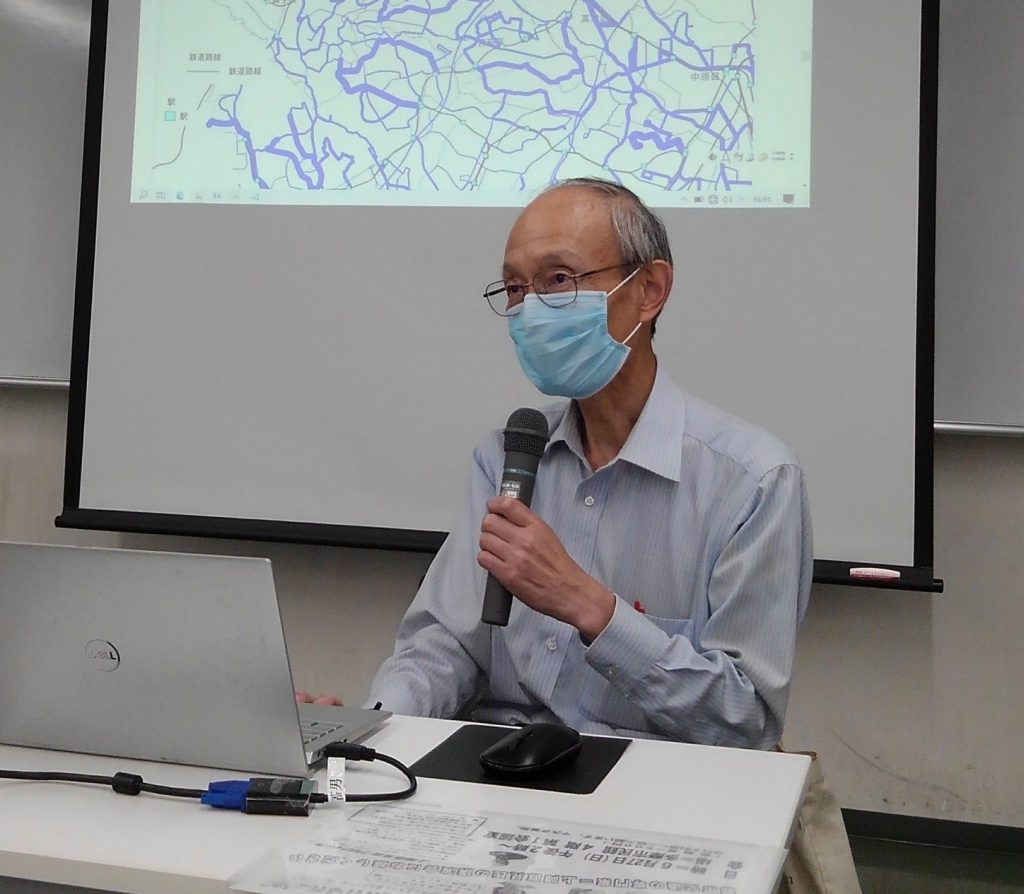
講演する上岡氏。 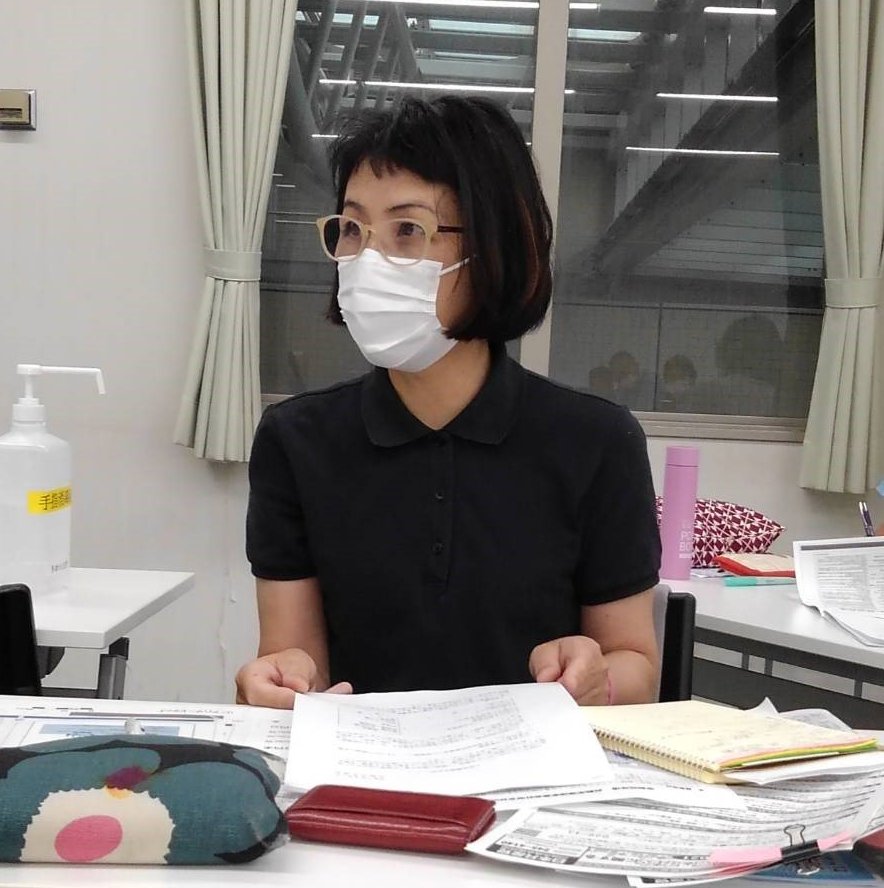
私も講演に聞き入りました。
6月27日(日)午後、多摩市民館にて、都市交通の専門家である上岡直見先生(「環境経済研究所」代表)をお招きし、講演会を開催しました。参加者は27名。お声がけしたところ「身近なテーマなのでぜひ」「興味があります」と、久々にお会いする方や、こうした集会には初参加の方もあり、うれしいかぎりでした。
私の担当地域である多摩区南部は、JR南武線中野島駅臨時北口改札の延長やバリアフリー、堰・宿河原地域へのバス路線新設、三田地域の小田急バス減便問題など、公共交通に関する地域要求が山積。
私も議会で質問してきましたが、とりわけこの1年間は「コロナによる減収で厳しい経営状況」をうたい文句に、改善の方向性は見出せぬままです。
そんななか、やはり市民の「交通アクセス権」という根本的なところから学びなおそう、そんな機運が高まっての講演会の実施となりました。
上岡先生はプロジェクターを使い、コロナと公共交通の関係性や、川崎市多摩区の人口、地形特性、鉄道やバス等の交通網など、豊富なグラフや地図を画面に示しながら、公共交通のありかたについてわかりやすく解説。
コロナでも交通格差が生じていること(年収が少ないほどリモートワークできていない現実)、川崎市各区からワクチン接種会場へ行くにもバスや鉄道がないとアクセス距離に大きな差が生じること、また、多摩区では総合医療機関までの平均アクセス距離は1.9キロになり、市内各区で最も長いことなど、驚きでした。さすが専門家!
また、国土交通省による地域公共交通の「クロスセクター効果」という考え方は、着目すべき視点だと思いました。「赤字だから」と鉄道やバスなどへの補助金を廃止すれば、公共交通を減らすことが、かえって行政コスト、利用者の負担を増加させることになる。その見極めをしっかり行うべきだということを、政府機関が示しているのです。
その真意がどこにあるかも含めて、今後の研究テーマになりそうです。
専門家を招いての講演会、学習会は、今後もさまざまなテーマで取り組んでいこうと思います。




